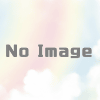動き出す妖怪展 NAGOYA|ゆらり、妖怪の気配
夏の名古屋で、“妖怪たちが、まるで今にも動き出しそうだ”と耳元で囁かれたような展覧会が始まります。
それは、絵画や戯画の中に眠る妖たちが、デジタルという霧をまとって動き出す特別なひとときです。
動き出す、時代を越えた百鬼夜行
「百鬼夜行絵巻」や「百物語」、「天狗」「河童」「付喪神」など、江戸・明治の絵師たちが描いた妖怪たち。
そのユーモアと不気味さが混ざった姿を、3DCGやプロジェクションマッピング、立体造形の力で、まるで夜の帳のように浮かび上がらせる空間だそうです。
深く、立ち上がる表情
映像と造形が重なり合い、妖怪たちはただの絵ではなく、立つ影となって立ち上がります。
鬼の怒り、河童の水かき、天狗の影のような鼻の形、付喪神の哀愁——静かな空気の中でも、触れられそうな存在感がにじみ出ているようです。
肌で感じる文化と歴史
妖怪画だけでなく、日本初の古書博物館・西尾市岩瀬文庫や小豆島の妖怪美術館の協力によって、文化や歴史のレイヤーが添えられているというのも興味深いことです。
イマーシブな映像とともに、日本人が長い時間をかけて育んできた妖怪の記憶に触れるような構成だと感じました。
百鬼夜行を歩く、参加型の体験
ただ観るのではなく、妖怪たちと練り歩くような「百鬼夜行パレード」もあるそうです。
鬼と一緒に歩くような気配が、自分の影のように寄り添う、そんな夜の幻に迷い込むような瞬間が、どこか日常のすぐ隣にあるように思えました。
雪明かりのような余韻
展示は、2025年7月19日から9月23日まで。会場は、名古屋・金山南ビル美術館棟(旧・ボストン美術館)です。
その期間中、昼間の妖怪は、暑さの中に潜む“涼やかな恐れ”のように静かに発声するものなのかもしれません。

問いかけの足音
妖怪とは、ただ恐ろしい存在ではなく、文化の影であり、暮らしの端にある感情の化身なのかもしれません。
ここには「見て、知って、歩く」ことで、忘れていた小さな不意の想像力を呼び覚ます余地がありそうです。