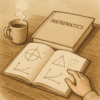あの人を、脳から消す技術|忘れたい記憶との距離
人の記憶というのは不思議なものです。
楽しい思い出は、ふとした瞬間に霞のように薄れていくのに、忘れたいことほど鮮やかに残ってしまう。
夜の静けさの中や、通りすがりの景色の中で、急に思い出したくない人の顔が浮かんでくることがあります。
その執着をどうにかしたい、と願うときに目にとまったのが、菅原道仁さんによる『あの人を、脳から消す技術』という本でした。
PR
脳科学から見た「忘れる」方法
この本は、現役の脳神経外科医である著者が、脳の仕組みを踏まえながら「忘れられない人」をどう扱うかを解説した一冊です。
忘れようとするほど逆に思い出してしまうことは、脳の記憶の働きによるものだそうです。
そのため、ただ「考えないようにする」のではなく、別の視点や行動によって記憶との距離を調整することが必要になると書かれていました。
七つのテクニックの存在
本書には「あの人を脳から消す7つのテクニック」として、具体的な方法が紹介されています。
たとえば記憶を映画のように映像化して距離を置く「映画化テクニック」、感情を紙に書き出して客観視する「書き出しテクニック」、視点を変える「リフレーミング」、今に意識を集中させる「今ここテクニック」など。
名前だけを眺めても、少し遊び心があって実践しやすそうに思えました。
どの方法も、過去を無理やり消すというよりは、記憶との関わり方を変えるための工夫に近いのだと感じます。
思い出を消し去るのではなく、生活の中で心の占める割合を減らしていく。
その考え方には、穏やかに自分を解放していくニュアンスがありました。
「消す」という言葉の奥にあるもの
書名にある「脳から消す」という表現は、少し強い響きを持っています。
けれども内容を知ると、それはただの切り捨てではなく、むしろ優しさを含んだ方法論に近いのだと理解できます。
誰かを強引に追い払うのではなく、自然と距離ができて心が軽くなるように導く技術。
その点で、忘れることを「努力」ではなく「選択」として提示しているのが印象的でした。
日常への応用を想像する
わたし自身も、頭の片隅から消えてほしい記憶に囚われることがあります。
そんなとき、もし映画のワンシーンのように切り取ってみたり、紙に書き出して机の引き出しにしまったりしたら、少し楽になるかもしれません。
日常の中で小さな実験のように取り入れてみたくなるヒントを感じました。
おわりに
『あの人を、脳から消す技術』は、過去の記憶に悩む人にとって、心の持ち方を少し柔らかくしてくれる本だと思います。
人間関係のしがらみや未練は、誰にとっても避けがたいもの。
だからこそ、脳科学という視点から新しい角度で向き合うことは、自分を守る手段になり得るのだと感じました。
忘れることは裏切りではなく、むしろ未来を歩むための静かな技術なのだと、この本の存在が教えてくれるように思います。

![あの人を、脳から消す技術 [ 菅原道仁 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2160/9784763142160_1_3.jpg?_ex=128x128)


![あの人を、脳から消す技術【電子書籍】[ 菅原道仁 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6398/2000017346398.jpg?_ex=128x128)





![あの人を、脳から消す技術[本/雑誌] / 菅原道仁/著](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_2004/neobk-3087107.jpg?_ex=128x128)