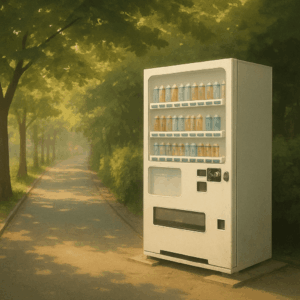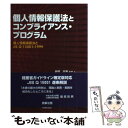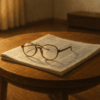街を歩いていて、ふと足を止めた。
自動販売機の前。
けれどそこには、金額の表示がない。
代わりに、小さなQRコードと「無料」という文字。
――いま、「無料自動販売機」というものが少しずつ広がっているのだそうです。
“お金を入れない”自販機
この仕組みは、企業のマーケティングや試供品配布の一環として生まれたもの。
利用者は、LINEの友だち登録や簡単なアンケート回答を条件に、コスメや飲料などのサンプルを受け取ることができます。
駅や商業施設に設置されていて、若い女性や学生を中心に人気を集めているそうです。
“無料”という言葉には、どこか不思議な響きがあります。
お金を介さない代わりに、わたしたちは“情報”を差し出す。
LINEの登録、アンケートの回答――それは、ほんの数秒の行為なのに、何かを交換している感覚が残る。
お金のかわりに、データが価値をもつ時代。
その光景は、ちょっとした未来の断片のようにも見えます。
「試す」ことで見えること
企業にとっては、こうした無料配布はマーケティングの一手段。
多くの人に手に取ってもらい、リアルな反応を知るためのものです。
けれど、利用者の側にとっても、“試す”という体験は小さな発見のきっかけになります。
たとえば、気になっていた化粧品を実際に使ってみることで、自分に合う・合わないが見えてくる。
無料であることよりも、“手を伸ばせる距離”が近くなることに意味があるのかもしれません。
災害時のもうひとつの“無料”
一方で、“無料自動販売機”にはもうひとつの形があります。
地震などの災害時に、自動的に中身が無償で提供される「緊急供給自販機」。
普段は普通の販売機として稼働しているのに、停電や地震を感知するとロックが外れ、水や食料が取り出せる仕組みになっているそうです。
こうした仕組みが各地で導入されているというニュースを読み、胸の奥が少し温かくなりました。
“無料”という言葉が、単なる宣伝ではなく、“支え合い”の形として存在しているのだと思うと。
お金のいらない世界の輪郭
それでもやっぱり、“無料”という言葉には、少しの警戒心もつきまといます。
便利さと引き換えに、わたしたちはどこまでの個人情報を渡しているのか。
PR
軽やかなクリックの裏に、目に見えない取引がある。
それを理解したうえで、心地よい距離感を選び取ることが大切なのかもしれません。
おわりに
無料自動販売機を前にしたとき、わたしは“ものの価値”について考えました。
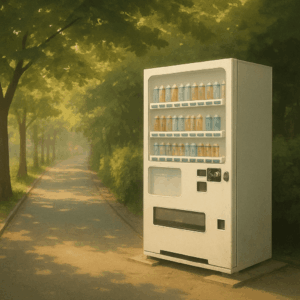
お金で支払うこと、情報で支払うこと。
どちらも、きっと人の行為の中に“選択”がある。
お金を入れずに商品が出てくる静かな音。
その裏側で、社会の仕組みも少しずつ変わっているのかもしれません。
PR
 770円(税込)【送料込】
770円(税込)【送料込】
楽天Kobo電子書籍ストア
<p>2015年に改正され、2017年5月30日に全面施行された個人情報保護法の改正ポイントを紹介し、日常業務でどのように個人情報を取り扱ったらよいか、事例を交えわかりやすく解説しています。<br /
 770円(税込)【送料込】
770円(税込)【送料込】
楽天ブックス
富士通エフ・オー・エム株式会社 (FOM出版) 富士通エフ・オー・エム個人情報 わかりやすい ドウナルドウスルコジンジョウホウホゴガヨクワカルカイセイタイオウ フジツウエフオーエムカブシキガイシャエフ
 354円(税込)【送料別】
354円(税込)【送料別】
もったいない本舗 おまとめ店
著者:浅川 浩出版社:日本実業出版社サイズ:単行本ISBN-10:4534038771ISBN-13:9784534038777■通常24時間以内に出荷可能です。※繁忙期やセール等、ご注文数が多い日に
 322円(税込)【送料別】
322円(税込)【送料別】
もったいない本舗 楽天市場店
著者:IT企業法務研究所, 松田政行出版社:日刊工業新聞社サイズ:単行本ISBN-10:4526053775ISBN-13:9784526053771■通常24時間以内に出荷可能です。※繁忙期やセール
 255円(税込)【送料込】
255円(税込)【送料込】
ネットオフ 送料がお得店
図解いちばんよくわかる最新個人情報保護法 単行本 の詳細 出版社: 日本実業出版社 レーベル: 作者: 辻畑泰喬 カナ: ズカイイチバンヨクワカルサイシンコジンジ
![【中古】 図解 いちばんよくわかる 最新 個人情報保護法 /]() 576円(税込)【送料別】
576円(税込)【送料別】
古本買取本舗 楽天市場店
著者:辻畑 泰喬出版社:日本実業出版社サイズ:単行本ISBN-10:4534055021ISBN-13:9784534055026■通常24時間以内に出荷可能です。※繁忙期やセール等、ご注文数が多い日
 400円(税込)【送料別】
400円(税込)【送料別】
もったいない本舗 楽天市場店
著者:柴原 健次, 克元 亮, 福田 啓二, 井海 宏通, 山口 伝, 鈴木 伸一郎, 藤谷 護人, 宮崎 貞至出版社:日本能率協会マネジメントセンターサイズ:単行本ISBN-10:482074771
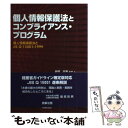 295円(税込)【送料別】
295円(税込)【送料別】
もったいない本舗 楽天市場店
著者:鈴木 正朝出版社:商事法務サイズ:単行本ISBN-10:4785711914ISBN-13:9784785711917■こちらの商品もオススメです ● プライバシーと高度情報化社会 岩波新書14
 490円(税込)【送料別】
490円(税込)【送料別】
もったいない本舗 楽天市場店
著者:個人情報保護法研究会出版社:保険六法新聞社サイズ:単行本ISBN-10:4901799029ISBN-13:9784901799027■こちらの商品もオススメです ● 納税者番号制とは何か 岩波
 598円(税込)【送料別】
598円(税込)【送料別】
もったいない本舗 楽天市場店
著者:柴原 健次, 克元 亮, 福田 啓二, 井海 宏道, 山口 伝, 鈴木 伸一郎, 中村 博, 坂東 利国出版社:日本能率協会マネジメントセンターサイズ:単行本ISBN-10:4820748866