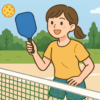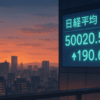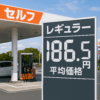アメリカに新しい製鉄所を──日本製鉄の決断に思うこと
最近、ニュースで「日本製鉄がアメリカに新しい製鉄所を建設する計画がある」と知りました。
その報道を見て、あれ、これってとても大きな話なのでは?と、胸の中が少しざわつきました。
というのも、日本製鉄が製鉄所を新設するのは、1971年の大分製鉄所以来とのこと。
50年以上ぶりという節目の決断は、鉄と火の歴史に新しい1ページを刻むものになるのだと思います。
しかもその舞台がアメリカ。
日本の企業が、国を超えてインフラの根幹に関わるような動きをするとき、そこにはたいてい、ただの経済合理性を超えた意味があるような気がします。
もちろん、世界的な需要の高まりや、米国内での製鋼需要を背景にした経営判断であるのは間違いないのでしょう。
でも、そこにはきっと、「技術」と「信頼」を根っこにした、日本製鉄らしい哲学があるのではないでしょうか。
今回の計画では、米国政府との合意のもと「ゴールデンシェア」が設けられたり、取締役の過半数を米国市民が担うといった、安全保障やガバナンスへの配慮もされています。
そうしたルールの中で、日本企業が現地の期待と信頼を得ながら、新しいものづくりの場を築こうとしている。
その姿勢には、どこか凛とした佇まいを感じてしまいました。
ふと、遠い昔に社会の授業で見た「製鉄所の煙突」の写真を思い出しました。

あれはたしか、大分製鉄所だったはずです。
時代の熱気がもくもくと立ち昇っているような、そんな風景でした。
それから何十年も経ち、環境への配慮やデジタル制御技術の発展によって、製鉄の現場も大きく変わったのでしょう。
それでも、鉄をつくるという行為には、どこか原始的な力強さがあります。
わたしたちの暮らしの「骨格」を担うものづくり──それは、目に見えないけれど、確実に世界を支えている。
今回のニュースから、そんなことを考えてしまいました。
技術と信頼を積み重ねていくことは、簡単なことではありません。
だからこそ、50年以上ぶりの「新設」という響きが、これほど心に残るのかもしれませんね。
PR
![日本製鉄の転生 巨艦はいかに甦ったか [ 上阪 欣史 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4236/9784296204236_1_5.jpg?_ex=128x128) 1,870円(税込)【送料込】
1,870円(税込)【送料込】
楽天ブックス
上阪 欣史 日経BPニホンセイテツノテンセイキョカンハイカニヨミガエッタカ ウエサカヨシフミ 発行年月:2024年01月22日 予約締切日:2024年01月21日 ページ数:288p サイズ:単行本
 1,870円(税込)【送料込】
1,870円(税込)【送料込】
楽天Kobo電子書籍ストア
<p>USスチールを2兆円で買収する大胆な決断は、この変革の延長線上にあった!</p> <p>過去最大の最終赤字4300億円を計上した年から約5年、瞬く間に復活し戦線を拡大する日本製鉄。<br />
 1,870円(税込)【送料込】
1,870円(税込)【送料込】
bookfan 2号店 楽天市場店
※商品画像はイメージや仮デザインが含まれている場合があります。帯の有無など実際と異なる場合があります。著者上阪欣史(著)出版社日経BP発売日2024年01月ISBN9784296204236ページ数2
 730円(税込)【送料別】
730円(税込)【送料別】
ネットオフ 送料がお得店
"日本製鉄の転生 " の詳細 出版社: 日経BP レーベル: 作者: 上阪欣史 カナ: ニッポンセイテツノテンショウ / ウエサカヨシフミ サイズ: 単行本 関連
 1,980円(税込)【送料込】
1,980円(税込)【送料込】
bookfan 2号店 楽天市場店
著者新日本製鉄(編著)出版社日本実業出版社発売日2007年01月ISBN9784534041753ページ数169Pキーワードからーずかいてつのみらいがみえる カラーズカイテツノミライガミエル しんにほ
 595円(税込)【送料込】
595円(税込)【送料込】
VALUE BOOKS
◆◆◆非常にきれいな状態です。中古商品のため使用感等ある場合がございますが、品質には十分注意して発送いたします。 【毎日発送】 商品状態 著者名 上阪欣史 出版社名 日経BP 発売日 2024年01月
 1,870円(税込)【送料別】
1,870円(税込)【送料別】
bookfan 1号店 楽天市場店
※商品画像はイメージや仮デザインが含まれている場合があります。帯の有無など実際と異なる場合があります。著者上阪欣史(著)出版社日経BP発売日2024年01月ISBN9784296204236ページ数2
 484円(税込)【送料別】
484円(税込)【送料別】
もったいない本舗 楽天市場店
著者:日鉄ヒューマンデベロプメント出版社:学生社サイズ:新書ISBN-10:4311700350ISBN-13:9784311700354■通常24時間以内に出荷可能です。※繁忙期やセール等、ご注文数
 69,091円(税込)【送料別】
69,091円(税込)【送料別】
タイヤのヘラクレス
※純正がスチールホイール装着車の場合はボルトの長さが足りません。 必ず別途専用ナットをお買い求めの上お取り付け下さい。 日本製鉄(旧新日鐵住金)のトラック・バス用アルミホイールです。 1980年からア
 712円(税込)【送料別】
712円(税込)【送料別】
もったいない本舗 楽天市場店
著者:新日本製鐵秘書部広報室出版社:丸善出版サイズ:新書ISBN-10:4621050672ISBN-13:9784621050675■こちらの商品もオススメです ● グローバリゼーションとは何か /

![日本製鉄の転生 巨艦はいかに甦ったか [ 上阪 欣史 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4236/9784296204236_1_5.jpg?_ex=128x128)